ここでは、航空大学校の倍率の実態や試験段階ごとの突破率、対策法までを徹底解説します。
「倍率が高いって聞いたけど本当?」「どの試験が一番難しいの?」「合格するには何を準備すればいい?」そんな疑問や不安に、やさしく丁寧にお答えします。
航空大学校を目指すあなたが、不安を自信に変えて一歩踏み出せるように、受験前に知っておきたい情報をぎゅっと詰め込みました!
この記事を読むとわかること
- 航空大学校の倍率が高い理由と過去5年の推移
- 試験段階ごとの難易度と具体的な対策方法
- 合格者の特徴と不合格になりやすい落とし穴
航空大学校の高い倍率の基本情報と重要性
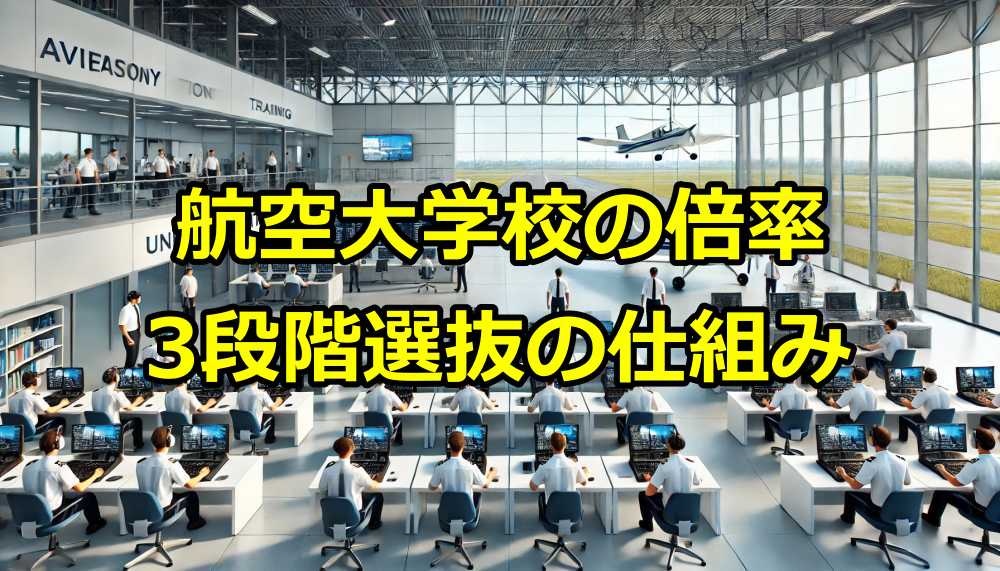
「航空大学校 倍率」で検索する人の多くは、受験の難易度や合格の可能性を知りたいと考えています。
しかし、倍率という言葉の意味や、どこでどのように影響するのかをしっかり理解している人は意外と少ないかもしれません。
この章では、航空大学校の倍率が持つ意味とその重要性を丁寧に解説していきます。
倍率とは何か?航空大学校における定義
倍率とは「志願者数を合格者数で割った数値」であり、合格の難易度を表す代表的な指標です。
たとえば、受験者が1,000人いて合格者が100人であれば倍率は10倍となります。
航空大学校ではこの倍率が非常に高く、特に一次試験から三次試験までの過程でどんどん絞られていくのが特徴です。
倍率の計算方法
倍率は基本的に「受験者数 ÷ 合格者数」というシンプルな計算式で求められます。
航空大学校では一次試験、二次試験、三次試験の各ステージごとに倍率が公表されています。
このため、それぞれの段階での通過率をチェックすることが非常に重要です。
合格率との違い
倍率と合格率は混同されがちですが、まったくの別物です。
合格率は「合格者数 ÷ 受験者数」で計算され、合格する可能性をパーセンテージで表す指標です。
例えば倍率が10倍でも、合格率にすると10%ということになります。
つまり、倍率は「どれくらい競争が激しいか」を示し、合格率は「自分が合格する確率」を示すものなのです。
航空大学校の試験制度と倍率の関係
航空大学校は一般的な大学と異なり、筆記試験だけではなく身体検査や適性検査などがある3段階の選抜方式を取っています。
この構造が、倍率の高さや試験の独特さに直結しています。
どの試験段階で何が問われるのか、そしてなぜそこで落ちる人が多いのかを理解することが、倍率を突破するカギとなります。
3段階選抜の仕組み
航空大学校の試験は一次試験(学科)、二次試験(身体検査・適性検査)、三次試験(面接・飛行適性検査)と続く、段階的な選抜方式が採用されています。
それぞれの試験ごとに受験者数が減っていくため、最終的な倍率が非常に高く感じられるのです。
特に身体検査や適性検査は、学力だけでは乗り越えられない難所です。
倍率が高くなる構造的な理由
航空大学校は毎年定員が非常に限られていることに加え、人気職業であるパイロットを目指す学生が多く志望します。
その結果、自然と倍率が高くなってしまうのです。
また、3段階の選抜方式で一貫して高い基準が求められることも、受験のハードルを上げる要因となっています。
航空大学校の高い倍率推移|過去5年間のデータ比較
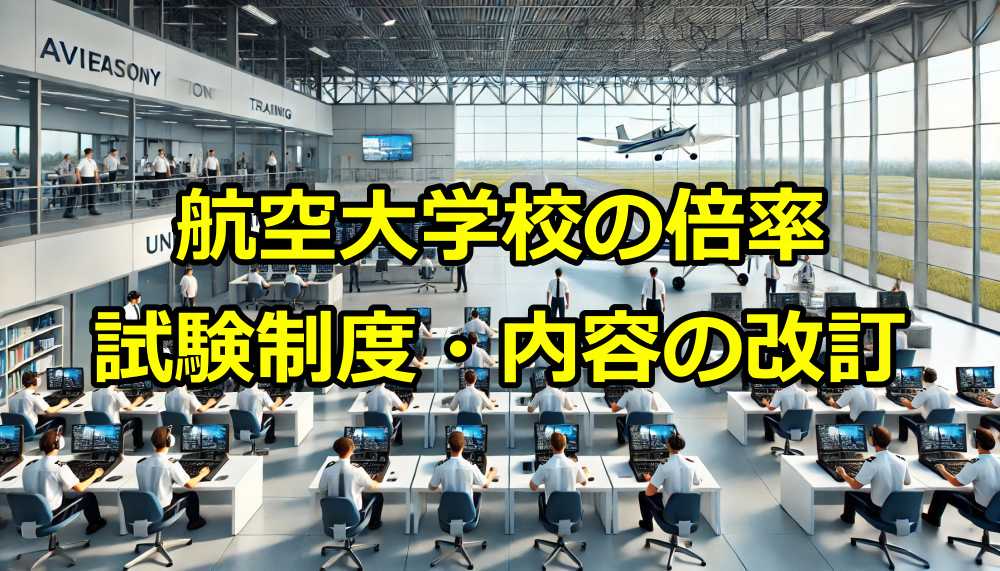
「倍率が高い」とよく言われる航空大学校ですが、それは一体どの程度なのか。
また、年ごとに倍率がどう変化しているのかを把握することは、受験戦略を立てる上で非常に大切です。
ここでは過去5年間の倍率データと、その変動の背景についてわかりやすく解説していきます。
過去5年間の倍率データ
航空大学校の倍率は年によって変動がありますが、常に高水準を維持しています。
過去のデータから傾向を知ることで、自分が受験する際の心構えや対策の参考になります。
年ごとの倍率一覧(表形式)
以下は、令和2年から令和6年までの航空大学校入学試験における倍率の一覧です。
倍率は「出願者数 ÷ 定員」で計算された概算値となっています。
| 入学年度 | 定員 | 出願者数 | 倍率 |
| 令和2年(67回生) | 108名 | 945名 | 約8.4倍 |
| 令和3年(68回生) | 108名 | 1,115名 | 約10.3倍 |
| 令和4年(69回生) | 108名 | 1,220名 | 約11.3倍 |
| 令和5年(70回生) | 108名 | 1,117名 | 約10.3倍 |
| 令和6年(71回生) | 108名 | 1,208名 | 約11.2倍 |
受験者数・合格者数の変化
出願者数は年々増加傾向にあり、特に令和4年以降は1,200人を超える年が続いています。
一方で定員は108名で固定されており、合格者数もほぼ一定です。
つまり、受験者が増えれば増えるほど、倍率は自然と上がってしまう構造となっています。
この状況は「人気があるから倍率が高い」というだけでなく、構造的に高倍率になりやすい設計だということを意味しています。
倍率変動の背景にある要因
単に受験者が多いから倍率が高い、というだけではありません。
倍率の上下には制度的・社会的な背景も深く関係しています。
ここでは、主な3つの要因を解説します。
募集定員の変更
航空大学校の募集定員は以前「72名」でしたが、平成30年度から「108名」に拡大されました。
この変更により一時的に倍率は下がりましたが、その後すぐに志望者数が増え、倍率は再び上昇しています。
つまり、定員が増えたからといって受かりやすくなるとは限らないのです。
試験制度・内容の改訂
近年、航空大学校では試験制度の見直しが行われつつあります。
今後導入が検討されているのは「女性枠の新設」や「数学IIIなどの理系科目の再評価」、さらには「総合型選抜のような柔軟な方式」などです。
このような変更が実施されれば、受験層が変化し、倍率にも新たな影響を与える可能性があります。
航空業界の需要と志願者の増減
航空業界全体の動向も、受験者数に大きく影響します。
パイロット不足が叫ばれる中、航空大学校の注目度はさらに高まりつつあります。
また、民間航空会社の採用拡大やテレビ・SNSでの報道なども、受験希望者の増加に拍車をかけているのが現状です。
航空業界の仕事や進路を、職種ごとに整理して全体像を知りたい方は
👉 航空業界の進路をまとめたガイドはこちら
試験段階別の倍率の高さと合格率のリアル

倍率は全体の数字だけを見ても、本当の難易度はわかりません。
大切なのは、どの試験段階でどれくらいの人数が絞られるのかを知ることです。
この章では、一次・二次・三次試験それぞれの倍率や特徴、合格率の実態を詳しく解説していきます。
一次試験(筆記)の倍率と突破率
一次試験は、航空大学校受験の最初の関門です。
この段階では、学力勝負になるため、合格に必要な点数や問題の傾向を押さえておくことが重要です。
ここを突破できるかどうかで、その後の展開が大きく変わってきます。
問題傾向と必要な点数
一次試験の科目は「英語」と「総合(数学・物理・気象・資料読解など)」の2つです。
過去問の傾向から判断すると、合格には全体の7〜8割程度の得点が必要とされています。
基礎問題が多い一方で、時間配分と処理スピードが合否を分けるポイントになります。
科目別の難易度と対策法
英語ではリスニング・長文読解・文法がバランスよく出題されます。
数学・物理は高校基礎レベルが中心ですが、応用問題も一部含まれており、ミスの少なさがカギです。
総合対策としては、過去問を中心に「問題形式に慣れる」ことが最優先です。
二次試験(身体検査・学科)の倍率
一次試験を通過したら、次は身体条件と適性がチェックされる二次試験です。
ここでは、学力だけでなく、航空身体基準に合致しているかが問われます。
受験者の中にはここで不合格となる方も多く、見落とされがちですが非常に重要な関門です。
身体条件のチェック項目
航空大学校の受験には「視力・色覚・身長・体重・聴力」などの制限があります。
裸眼視力が一定以上であることや、色覚に異常がないことが求められます。
特に視力と色覚は厳格に審査されるため、事前の確認が必須です。
落ちやすいポイントと注意点
基準未満の視力や色覚異常が見つかると、その時点で不合格となります。
また、学科では反応速度や判断力を問う問題もあり、知識だけでは通過できません。
事前に「自分の身体条件が航空基準を満たしているか」を確認することが、最も重要です。
三次試験(面接・適性検査)の倍率
三次試験は最終段階で、人物評価と飛行適性が試される内容です。
ここでは知識や身体能力だけではなく、人間性や判断力といった「パイロットにふさわしいか」が見られます。
油断せず、事前準備を徹底することが合格のカギです。
面接の評価ポイント
質問の中心は「志望動機」「学生時代の経験」「自己PR」などです。
受け答えの内容だけでなく、表情・声のトーン・姿勢なども評価の対象になります。
一貫した志望理由と明確な目標意識が重要です。
飛行適性検査の内容と準備法
飛行適性検査では、模擬操縦装置を使って「反射」「空間認識」「同時処理能力」などが問われます。
シミュレーターを使った訓練や、反射神経を鍛える簡単なゲームも対策に有効です。
この検査は慣れと経験値がものを言うため、早めの準備が非常に大切です。
段階ごとの合格率比較
「どこで落ちる人が多いのか?」は、受験者にとって最大の関心ごとです。
ここでは、一次〜三次までそれぞれの通過率の傾向を整理します。
戦略的な対策を立てるためにも、データを押さえておきましょう。
どの段階で落ちる人が多いか
もっとも多くの人が落ちるのは一次試験です。
倍率が約10倍のため、約9割がここで脱落する計算になります。
二次では身体条件・健康面での不適合者、三次では人物面・適性面での評価が低い人が落とされます。
段階別に必要な対策の方向性
一次試験:基礎力を中心に過去問で出題形式に慣れる。
二次試験:身体基準の事前確認と、反応テスト・適性チェックのトレーニング。
三次試験:面接練習と模擬訓練での慣れが成功の鍵。
各段階ごとの弱点を分析し、個別に対策を立てることが最短ルートです。
航空大学校の倍率が高い理由とは?
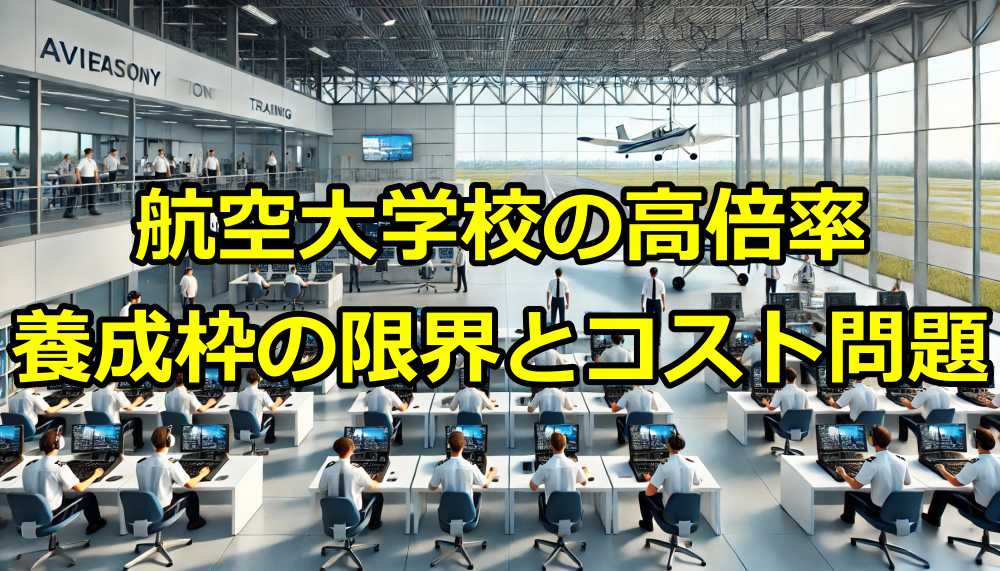
「なんでこんなに倍率が高いの?」と疑問を持つのは当然です。
倍率の高さには、単なる人気だけでなく、複数の構造的な理由があります。
受験を考えているあなたが納得できるように、理由をひとつひとつ分かりやすく解説します。
航空大学校の人気の高さ
まず第一に、航空大学校は多くの人に「憧れ」の対象となっています。
パイロットや航空に関わる仕事に対する夢を持っている人が多く、注目度が非常に高いです。
受験者層の特徴と志望動機
受験者には、飛行機や空を飛ぶことに強い興味を持っている人が多いです。
「空の安全を支えたい」「人を飛ばす仕事がしたい」「海外との仕事ができそう」という動機がよく見られます。
情熱や夢が動機である受験者が多いため、競争率が上がるわけです。
募集定員の少なさによる影響
人気が高くても、定員が少ないと倍率は自然と高くなります。
定員の増減があっても、その影響は志望者の増加によって打ち消されることが多いです。
民間大学との比較
多くの私立大学・専門大学では、定員に比較的余裕がある場合があります。
一方で航空大学校は訓練施設・設備・教官などにかかるコストが大きく、定員を大幅に増やすことが難しいという特徴があります。
限られた枠で多くの志望者が集まる構図になっているのです。
養成枠の限界とコスト問題
航空大学校では訓練用施設・飛行機・教員・保守管理など高いコストがかかります。
これらのコストをまかなうための予算の制約があり、人数を大幅に増やすことが簡単ではありません。
また、訓練の安全や質を保つことが求められるため、一度に多くの学生を抱えることもリスクがあります。
試験内容の特殊性
航空大学校の試験は、一般の大学入試とはかなり異なる特徴があります。
学力のほかに身体的・適性・性格など多面的に評価されるため、万全な準備が必要です。
他の大学と異なる試験内容
一般大学入試では筆記試験中心ですが、航空大学校では筆記の他に適性検査・身体検査・面接などがあります。
特に身体検査の視力・色覚基準や、飛行に耐える身体能力など、特殊な条件が求められます。
学科以外の要素が合否に大きく関わる点で、競争が激しくなるのです。
学力以外の選抜要素が多い
適性検査では反射神経や判断力など、「場面対応力」が求められます。
面接では志望動機・人柄・コミュニケーション能力など、学力では測れない部分も重視されます。
また、2027年度入試からは女性枠や総合型選抜の新設が予定されており、人物中心の評価が増える方向にあります。
高い倍率を突破するための戦略と対策
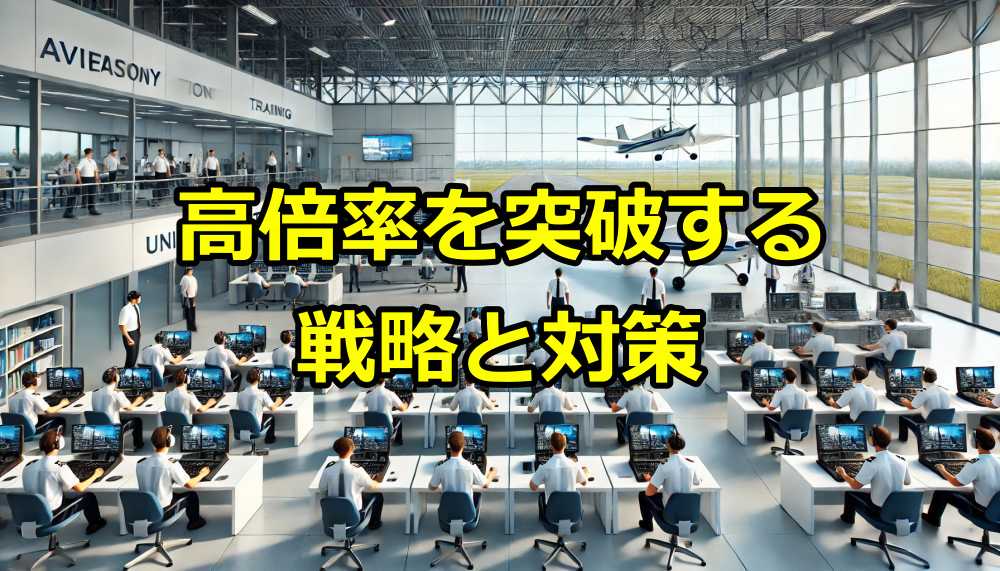
航空大学校の受験は倍率が高く、しっかりとした戦略と対策がなければ突破は難しいです。
ですが、何を・どのように・いつ取り組めば良いのかを知っていれば、無駄なく効率的に合格へと近づけます。
ここでは、試験段階ごとに必要な対策をわかりやすく紹介していきます。
一次試験の学科対策
一次試験は航空大学校の最初の関門であり、筆記試験による学力チェックが中心です。
ここでしっかり得点できるかどうかが、その後の試験へ進めるかを左右します。
まずは過去問と頻出分野の理解から始めてみましょう。
過去問活用と頻出分野
航空大学校では過去問の傾向が比較的安定しており、繰り返し出題される分野もあります。
特に「英語の読解」や「数学・物理・気象」などは頻出で、確実に押さえておきたいポイントです。
過去問を通して出題形式に慣れ、出やすい問題から優先的に対策しましょう。
時間配分と勉強スケジュール
試験時間内に全問を解ききるには、スピードと正確性が求められます。
過去問を解く際は、実際の試験時間で解く「タイムトライアル形式」を取り入れると効果的です。
勉強スケジュールは「弱点補強 → 頻出分野の徹底 → 実戦演習」の順で組み立てると無駄がありません。
身体検査・適性検査への対策
一次試験を突破しても安心はできません。
二次試験の身体検査・適性検査では、学力以外の部分での“落とし穴”がたくさんあるからです。
事前準備を徹底することで、ここでの不合格リスクを減らせます。
事前準備できる項目
視力・色覚・身長・体重・聴力・呼吸器など、身体検査でチェックされる項目は多岐に渡ります。
特に視力と色覚は合否を分ける重要ポイントです。
普段からの健康管理や、必要であれば早めの医療相談も対策のひとつです。
見落としやすい落とし穴
自覚のない色覚異常や、視力の安定性、心電図・肺機能などが基準を下回ると不合格になることがあります。
また、試験当日の体調不良がパフォーマンスに影響することもあるため、生活習慣の見直しも重要です。
「自分は大丈夫」と思わず、早めの健康チェックを行いましょう。
面接・飛行適性検査で差をつける
三次試験では受験者のレベルがほぼ均等になるため、「人間力」や「適性」の差が合否を分けます。
ここでは、事前に準備しておくことで評価を上げられるポイントを紹介します。
質問例と回答のコツ
よく聞かれる質問には「志望動機」「将来の目標」「過去の挫折経験とその克服」などがあります。
回答はできるだけ具体的に、自分だけの言葉で話すことが大切です。
面接練習を録音・録画して客観的に振り返ると、改善点が見えてきます。
実技試験の準備と心構え
飛行適性検査では模擬操縦装置を使って、判断力・反射神経・空間認識力などを測定されます。
市販のフライトシミュレーターやトレーニングアプリで「慣れ」を作ることが有効です。
本番で緊張しすぎないためには、場慣れしておくことが何より重要です。
合格者の共通点と学習傾向
実際に合格した人たちには、共通する思考や習慣があります。
「自分に足りない部分」を冷静に見つめ、着実に対策を続けていたことが共通点です。
失敗パターンと照らし合わせて、自分の勉強方法を見直してみましょう。
受かる人の思考と行動
合格者は「早期に対策開始」「定期的な振り返り」「弱点への集中補強」を徹底していました。
量ではなく、質の高い学習と明確な計画性が合格を引き寄せたポイントです。
よくある失敗パターン
失敗する人の多くは、「過去問だけに頼る」「苦手を放置」「直前に詰め込む」といった行動に陥りがちです。
また、「健康管理を怠って身体検査で不合格」「面接を軽視して減点」といったケースも目立ちます。
対策は「全部やる」ではなく、自分に必要なものを的確に選び抜くことが大切です。
倍率が高くても航空大学校を目指す価値とは

「倍率が高いから無理かも…」そう感じる方も多いかもしれません。
でも、航空大学校にはその高倍率を超えてでも挑戦する価値があります。
この章では、その理由を進路・他校との比較・やりがいという3つの視点からお伝えします。
航空大学校卒業後の進路
航空大学校を卒業すると、どんな道が広がっているのか気になりますよね。
実は卒業後の選択肢はとても幅広く、民間だけでなく公的分野への就職実績も豊富です。
ここでは代表的な進路を紹介します。
民間航空会社への就職率
航空大学校の最大の魅力は高い就職実績です。
ANA・JALをはじめとする大手航空会社への就職者が多く、毎年安定した採用が続いています。
特に訓練で得られる飛行時間や技術力が評価され、即戦力として迎えられているのです。
自衛隊や他分野への選択肢
民間だけでなく、自衛隊・航空局などの公的機関にも進路が開かれている点は大きなメリットです。
パイロット以外でも、航空管制、整備、教育分野など多様な職種で卒業生が活躍しています。
「空に関わる仕事がしたい」という夢を、様々な形で実現できる環境が整っているのです。
他の養成機関との比較
航空大学校の価値を正しく理解するには、私立大学や民間養成機関と比較してみるのが効果的です。
ここでは「教育の質」「費用」「キャリア実績」に分けて、その違いを見ていきましょう。
私立大学航空コースとの違い
私立大学の航空コースも魅力的ですが、訓練機材や飛行時間に差があることが多いです。
また、航空大学校は国の運営による信頼性と伝統があり、企業側からの評価も高いのが特徴です。
教育の質・現場の即戦力としての評価では、一歩リードしている印象です。
費用・期間・実績の差
私立大学や民間養成スクールでは、学費や訓練費が数百万円〜1,000万円以上かかることもあります。
一方、航空大学校は国立機関であり、費用を抑えながらプロの教育が受けられるのが魅力です。
さらに、実績としても大手エアラインへの就職者数で高い水準を保っています。
航空大学校の魅力とやりがい
航空大学校には、数字では表せない“学びの質”や“人とのつながり”があります。
夢を追う仲間と切磋琢磨する環境は、人生において大きな財産となるはずです。
ここでは実際の声やキャリア例をもとに、その魅力をお伝えします。
実際の学生の声
「本当に濃い時間を過ごせた」「毎日が挑戦の連続だった」「仲間との信頼関係が一生ものになった」
これらは航空大学校に通った学生からよく聞かれる感想です。
パイロットとしての技術だけでなく、人間力が磨かれる環境が整っています。
卒業生のキャリアと満足度
卒業生の多くは、第一線の航空会社や官公庁で活躍しています。
就職先での評価も高く、航空大学校出身というだけで信頼されることも多いようです。
また、「自分の夢を実現できた」「大変だったけど最高の3年間だった」という高い満足度の声も多数寄せられています。
【まとめ】航空大学校の高い倍率を正しく理解しよう

ここまで、航空大学校の倍率の推移や各試験段階での特徴、対策法や進路の魅力について解説してきました。
倍率が高いからこそ、正しい理解と事前の準備がカギを握ります。
最後に、知っておくべき重要ポイントを振り返り、受験準備に役立つチェックリストを紹介します。
倍率に関する重要ポイントの総復習
航空大学校の倍率は、例年約8〜11倍前後で推移しており、非常に高水準です。
倍率は「受験者数÷定員」であり、一次〜三次まで段階ごとの選抜が行われます。
最も多くの人が落ちるのは一次試験ですが、身体検査や適性検査でも意外に不合格が出ます。
倍率の背景には、人気の高さ、定員の少なさ、訓練コストの制約、試験の特殊性などがあります。
しかし、その分得られる経験・進路・満足度は、倍率を超える価値があります。
受験前にやるべき準備チェックリスト
以下の項目を確認することで、自分の準備状況を見直してみましょう。
- 過去問を繰り返し解いている(時間配分の意識あり)
- 英語・数学・物理・気象など、頻出分野を重点的に対策している
- 身体検査の基準(視力・色覚・身長など)を事前に確認した
- 適性検査・飛行シミュレーションの対策を始めている
- 面接の練習を行い、自分の言葉で話せるように準備している
- 航空大学校を目指す志望動機が明確になっている
- 健康管理を意識した生活習慣を整えている
このチェックリストを参考に、自信を持って受験に臨める状態を目指しましょう。
航空大学校の扉は狭くても、入学後に広がる空は本当に大きな世界です。
諦めずに、コツコツ準備を重ねるあなたを全力で応援しています!


