航空障害灯の設置基準は、航空法第51条で定められており、高さ60m以上の建築物には設置義務があります。
さらに、高さ150mを超える建築物には中光度の航空障害灯が必要とされるなど、建物の高さによって基準が異なります。
この記事では、設計や管理に関わる方に向けて、最新の設置基準と免除条件、光度別のルールをわかりやすくまとめました。
航空障害灯の設置が必要な高さとその理由
航空障害灯の設置基準を知る上で、まず最初に押さえておきたいのが「どの高さから義務が生じるか」という点ですね。
この基準は、航空機の安全な飛行を確保するために定められており、主に航空法に基づいています。
特に都市部では高層ビルの建設が増えており、その都度この基準が適用されるケースも多くなっています。
この章では、60mと150mという二つの高さを基準とした設置義務の考え方を解説していきますね。
どのような建物にどの種類の灯火が必要になるのかを、具体的な条件とともにお伝えします。
設置義務は地表から60m以上の物件に発生
航空障害灯は、高さ60mを超える建物に対して設置が義務付けられています。
これは建物の用途や構造を問わず、屋上に突き出た設備やペントハウスなども含まれますよ。
例えば、非常用エレベーターの機械室などが60mラインを超える場合でも、対象になります。
この基準は、航空機が夜間や視界の悪い天候時に安全に飛行するために必要なものですね。
仮に屋上設備だけが60mを超えていても、その部分だけに灯火を設置するケースもありますよ。
150mを超える場合は中光度航空障害灯が必須
建物の高さが150mを超える場合には、さらに厳しい基準が適用されますね。
この高さでは、低光度では不十分とされ、中光度の航空障害灯の設置が義務となります。
中光度灯は明滅型が基本で、昼夜問わず航空機に対して明確な視認性を提供する役割がありますよ。
また、150mを超える場合には建物の頂部だけでなく、側壁への灯火設置も求められますね。
令和4年の基準改正により、周囲の視認性が十分に確保されている場合は、中光度灯の一部を低光度灯で代替できるようになりました。
この緩和措置により、条件を満たす建物では設置コストや施工負担の軽減が期待されています。
航空障害灯の種類と高さ別の設置基準

航空障害灯には、低光度・中光度・高光度といった種類があり、それぞれ適用される高さが異なりますね。
この章では、建物の高さごとに必要な灯火の種類と設置位置について詳しく見ていきましょう。
設置義務があるかどうかだけでなく、どの光度の灯火が必要かも重要なポイントですね。
また、建物の構造や形状によって設置の仕方が異なることもあるため、細かい点も確認しておきたいところです。
適切な灯火の選定と配置は、安全性はもちろん、コストや施工性にも影響を与える重要な判断材料ですよ。
60m以上150m未満の建物に求められる灯火
この高さの範囲では、基本的に低光度航空障害灯(約100cd)の設置が求められます。
建物の外形が視認できるよう、屋上の四隅やペントハウスの頂部などに設置されるケースが多いですね。
幅が45m未満の建物では、対角2箇所への設置でも基準を満たす場合がありますよ。
一方で、45mを超える建物では、より多くの灯火を設置する必要があります。
こうした設置数や位置の違いは、事前にしっかりと計画することが大切ですね。
150m以上の高層建築物への追加要件
150mを超える建物には中光度航空障害灯の設置が必要になります。
さらに、建物の側壁にも、一定間隔ごとに灯火を設置することが求められていますね。
例えば、地上150mまでの範囲に、52.5m以下の等間隔で低光度灯を交互に配置する形です。
また、建物幅が45mを超える場合は、出隅すべてへの設置が必要になるケースもありますよ。
このように、150mを超える場合は、より厳密な設計と計画が必要ですね。
ペントハウスやタラップへの対応基準
屋上にある設備や突起物も、高さに関わらず航空障害灯の対象となる場合があります。
例えば、ペントハウスや非常用階段の囲いなどが該当しますね。
高さ3mを超える突起がある場合は、その先端にも灯火が求められますよ。
一方で、高さが3m未満であれば設置が不要とされるケースもあります。
これらの判断は建物の設計段階から考慮しておくことが重要ですね。
旅先でも“日本のネット環境”を持ち歩こう。
海外に行くと、見慣れたサービスが使えない…そんな不便、もう感じなくて大丈夫!ExpressVPNなら、まるで日本にいるように動画やSNSもサクサク。
海外・国内・公共Wi-Fiでもしっかり守られるので、セキュリティも安心。
割引キャンペーン+30日間返金保証付き!
航空障害灯の免除規定と緩和条件
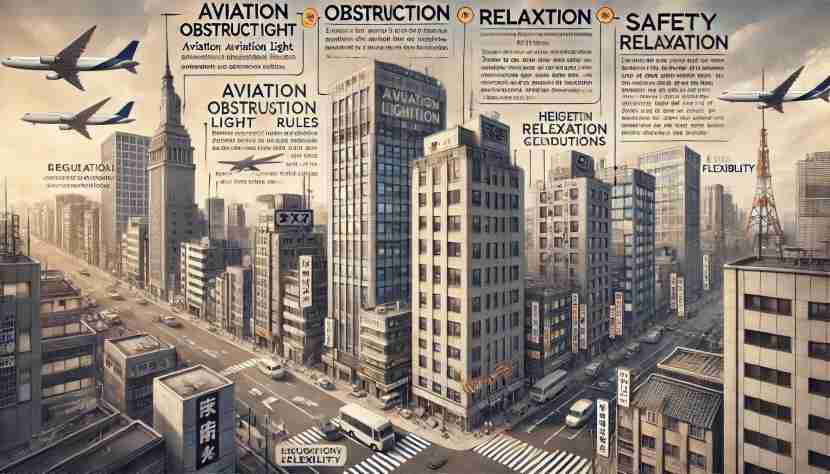
すべての建物が航空障害灯の設置を義務付けられるわけではないというのは、あまり知られていないかもしれませんね。
実は航空法では、一定の条件を満たせば設置を免除したり、設置基準を緩和することができるようになっています。
これは建築物の周囲に他の高い建物が存在する場合などに適用される規定で、都市部の設計では非常に重要なポイントですよ。
この章では、設置免除や低光度化の条件について、具体的な距離や高さのルールとともに解説していきます。
建設コストの最適化や申請業務の効率化にもつながる情報なので、ぜひ押さえておきたいですね。
周囲の建築物により免除が可能なケース
航空障害灯の免除が可能となるのは、周囲により高い建築物がある場合ですね。
たとえば、物件の半径500m以内により高い建物が存在し、その建物に航空障害灯が設置されていれば、免除対象になりますよ。
また、対象となる物件の海抜高よりも高い山や自然物が近隣にあるケースも、免除の条件に含まれることがあります。
必ず所轄の航空局に事前申請をして、免除許可を得る必要がありますので注意が必要ですね。
令和4年の改正では、昼間障害標識(塗装・標識)の設置に関しても免除基準が明確化されました。
高さ別に異なる免除条件の詳細
航空障害灯の免除条件は、建物の高さによっても変わってきますね。
60m以上100m未満の物件の場合は、2km以内により高い山があるか、500m以内に高い建物があることが条件です。
一方で、100m以上150m以下になると、免除の対象範囲が狭まり、条件も厳しくなってきますよ。
令和4年の改正では、ビル群として視認される地域においては、最も高い建物のみに中光度灯を設置すれば、他の建物には低光度灯での対応が可能になりました。
これにより、都市部における航空障害灯の設置計画が柔軟に対応できるようになっています。
免除対象ビル選定時の注意点
免除対象として利用する周辺建物の選定には慎重さが求められますね。
なぜなら、その建物が将来的に解体された場合、自身の建物が最も高い建物となってしまう可能性があるからです。
その結果、免除が取り消され、航空障害灯の設置が義務化されてしまうこともありますよ。
選定する建物は、なるべく新しく、長期的に残る可能性が高いものを選ぶのが望ましいですね。
また、建物の用途や所有者の意向も考慮しておくと、後のトラブルを防ぐことができますよ。
航空障害灯の点灯方式と管理運用のルール

航空障害灯は、設置するだけでなく、点灯や管理にも細かいルールが定められていますね。
故障や停電が発生した場合でも、安全性を損なわないようにするための措置が義務付けられています。
この章では、昼夜で異なる点灯ルールや、管理者として守るべき基本的なポイントについて説明していきます。
特に高層ビルや鉄塔を管理する企業にとっては、法令遵守と安全確保の両面で欠かせない知識ですよ。
トラブルを未然に防ぐための備えとして、しっかりと押さえておきたい内容ですね。
日中・夜間の点灯条件と点灯制御方法
航空障害灯の点灯は、昼と夜でルールが異なります。
中光度・高光度の灯火は基本的に常時点灯が必要ですが、低光度の灯火は夜間のみ点灯すれば良い場合もありますね。
点灯の制御は、照度センサーによって自動的に行われるのが一般的です。
令和4年の基準改正では、LED式航空障害灯の仕様についても詳細に明文化されました。
点滅回数、明滅比率、運転時間のタイマー管理、断線検知、交換時期の通知など、より厳密な管理が推奨または義務付けられています。
チャタリングを防ぐ照度差設定とは
点灯・消灯の制御においては、チャタリングという問題もあります。
これは、照度がちょうど閾値付近にあると、センサーが点灯と消灯を繰り返してしまう現象ですね。
チャタリングが発生すると、灯具の寿命が縮むだけでなく、誤動作によるトラブルにもつながります。
照度の設定には“ONになる照度”と“OFFになる照度”に差を持たせる必要がありますよ。
この設定を適切に行うことで、安定した運用が可能になりますね。
故障時の対応と非常電源の必要性
航空障害灯が故障した場合には、速やかな復旧対応が求められます。
これは航空機の安全を守るという観点からも、非常に重要な義務ですね。
また、非常電源の設置が必要なケースもありますよ。
特に緊急離着陸場を備える建物や、救助活動の対象になる施設では、4時間以上の電源供給が求められることもあります。
普段から予備電源の点検や交換体制を整えておくことが、法令遵守と安全管理につながるのです。
LED化によるメリットとコスト削減効果
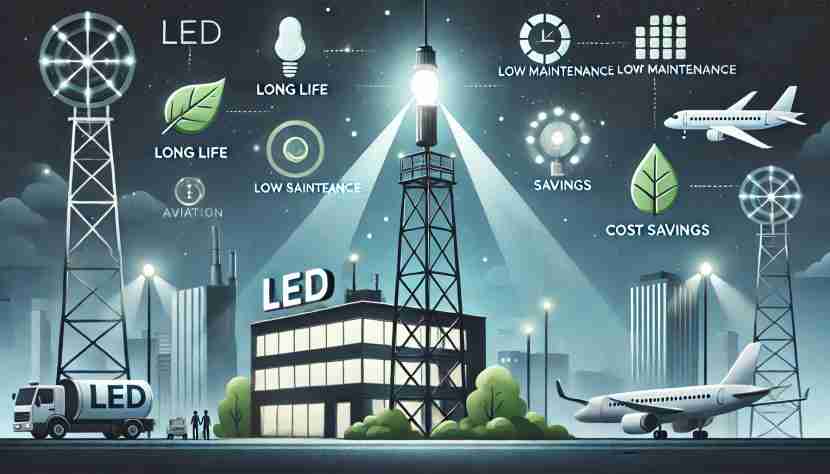
近年では、航空障害灯のLED化が進んでいます。
白熱灯やハロゲン灯と比較して、LEDは圧倒的に長寿命で、メンテナンスの手間も大幅に削減されますよ。
この章では、LED航空障害灯の特徴と導入による具体的なメリットをご紹介します。
コスト面の最適化だけでなく、環境への配慮にもつながる取り組みですね。
今後の建物計画において、LED化は欠かせない選択肢のひとつと言えるでしょう。
LED式航空障害灯の導入効果とは
LED式航空障害灯は、従来の電球型と比較して寿命が約10倍以上長くなっています。
これにより、定期的な交換作業の手間や高所作業に伴うリスクを大きく減らせますね。
光の拡散性や視認性も優れており、安全性を高めながら効率的な運用が可能です。
導入当初のコストはやや高めですが、長期的にはランニングコストが抑えられるため、結果として経済的ですよ。
環境への配慮という点でも、CO2排出量の削減に貢献できるのは大きな魅力ですね。
航空障害灯 設置基準と緩和ルールのまとめ
この記事では、航空障害灯の設置基準について、基本から最新の緩和条件まで幅広くご紹介しました。
特に60mと150mの高さが重要な分岐点であること、免除やLED化といった選択肢も存在することをお伝えしましたね。
設計や管理の現場では、これらの基準を正しく理解しておくことが、法令遵守と安全確保の第一歩となります。
ぜひこの記事を参考に、より安全で効率的な建物運用を進めていただければと思います。
今後も法改正や技術の進化に合わせた最新情報を追い続けることが大切ですね。


